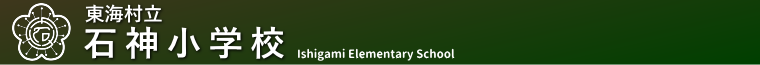
石神城は中世の城で、城主は佐竹氏家臣の石神小野崎氏です。天文15年(1546)頃,所領の境界をめぐって額田小野崎氏との間で合戦になり、その結果石神小野崎氏は敗北し、城から退去しました。
しかしその後、佐竹氏への戦功により領地の維持と帰城が認められます。慶長7年(1602)佐竹義宣の秋田移封に従ってこの地を去り、石神城は廃城になりました。

保存状態が非常によく、深い堀や土塁などがよく残っています。中心の郭の外にも土塁の一部が残っているほか、城の西側には城下町としての景観が見られ、南側には城主の石神小野崎氏の菩提寺である長松院などが立地しています。
石神小学校のすぐ西側に、大同元(806)年に摂津住吉神社(現在の大阪の住吉大社)の分霊を勘請し創立したと伝えられている住吉神社があります。住吉神社は、一般的に港や入江などの水にまつわる神社です。
昔は、久慈川が石神城側(竹瓦地区)に蛇行しており、この地は水辺となっていました。この神社は石神小野崎氏が崇敬し、石神城の鎮守としたそうです。

境内には「真杉(ますぎ)」と表現されている、天高く伸びる杉の大樹が今も数多くあり、石神小の学校便りの名前にもなっています。また、石神国民学校時代に、授業で使った土俵の跡が残っています。

神々の時代、日立の大みか神社の宿魂石に星神香々背男(ほしのかがせお)という悪神がおり、天手力雄命(あまのたぢからおのみこと)が祈念をこらしたところ、宿魂石が3つに砕け、石の頭部がこの場所に飛んできたそうです。(あとの2つは日立市石名坂と城里町石塚)
この伝説は石神の地名の由来になっていて、かつては「石頭」としていましたが、中世以降に「石上」と書くようになり、江戸時代にこの地を訪れた徳川光圀の命により「石神」としたといわれています。石神小学校の校名の由来です。
石神小学校が現在ある場所は、「中道前古墳群」と呼ばれ、別当山古墳、座応権現山古墳、茅山古墳、戸ノ内古墳など多くの古墳がありました。数多くの埴輪や土器、村指定文化財の直刀、三輪玉が出土しています。石神小学校の校庭には,茅山古墳の前方部が残されており、出土した埴輪は校舎内に展示してあります。


福島県を源流とする一級河川で、日立市と東海村の境界から太平洋に注いでいます。アユの生息数でも日本有数の河川で、初夏から秋にかけて釣りを楽しむ人々で賑わいます。アユだけでなく、サケも遡上するほか、数多くの鳥類、昆虫、植物が住んでいます。豊かな自然に親しもうと多くの人びとが訪れます。
石神小学区の久慈川では、古来から久慈川の伝統漁法である「サケ漁」が行われています。毎年秋には見学会が行われ、サケのアラ汁や焼きサケをいただけます。

国道6号線は、東京の日本橋から茨城県を通って宮城県仙台市に至る、総延長439.9kmの道路です。石神小学区を南北に通っている大動脈です。
「榊橋」は久慈川にかかり、東海村と日立市を結ぶ橋です。橋の名は、石神村の「神」と日立市土木内の「木」から付けられました。明治28年に木製の橋が架けられ、昭和5年にはコンクリート製になりました。現在の橋は平成11年に2車線が開通し、19年に4車線となっています。
